
こんにちは、ニムヒロです。
私は2025年電験三種に合格しました。
その成功体験からノウハウを発信し、皆さんにもこの成功体験を味わってもらいたいと思いブログを立ち上げました。
何故情報発信するのかはこちらに記載しています。↓
自己紹介〜私がブログを始めた理由「皆さんと成功体験がしたい!」〜
次受けるならどの資格?ということで、私の働く現場でも必要とされる、「エネルギー管理士」を受験しようと思い立ちました!
そこで出てくる悩みが、「熱分野」で受験するか、「電気分野」で受験するかです。
この最初の選択について、私の場合は「電気分野」を選択します!
理由は、電験3種に合格した直後であるからです。
同じように『電気分野を受験したい!』と考えている方は、一緒に頑張りましょう!!
この記事を読めばあなたがどちらを選べば良いかが分かります!
では皆さんはどっちを選択すればいいのか、分析していきたいと思います。
私と同じように電験3種から受験しようかなという方は、電験三種の概要についてこちらで紹介しています。↓
電験三種ってなに?試験概要や試験時間、取得メリットなど徹底解説!
エネルギー管理士を取得するメリット!
①エネルギー管理士は昇級昇格に影響する可能性あり!?
②転職に有利に!?
エネルギー管理士試験は、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」、いわゆる「省エネ法」に基づき試験を実施しています。
昨今の地球温暖化問題などでCO2を削減する取り組みが代表的ですが、これは全ての国が温室効果ガス削減に向けて取り組みを行うことが義務化されています。
日本は先進国であるため特に厳しい目標を掲げ取り組みを行っており、省エネに取り組む事が企業のアピールにもなり、省エネが世界に向けたビジネスへと変化しています。
一定量以上のエネルギーを使用する工場又は事業場は、最大で4人の「エネルギー管理者」を選任する必要があるため、資格合格者を重宝する事業場は多く存在します。
また、「エネルギー企画推進者」や「エネルギー管理員」を選任する場合、講習を受講することで選任資格を付与して貰えますが、更新講習も必要なため、資格保有者から選任することがほとんどかと思います。
これらは重要な役割のため、管理職もしくはそれに近い程の経験者が選任されることが多く、取得すれば昇級昇格に向けては大きなアドバンテージになる可能性があります!
また、免状発行には合格前後どちらでも構いませんが、1年の実務経験が必要なため、取得メリットが無い方もいると思います。
こういった方は、異動希望時や転職市場においてアピール要素となってくれるでしょう。
試験概要
①試験は年に1回。8月初週頃に実施される。
②「熱分野」と「電気分野」どちらで合格しても同じ資格!
③科目合格あり!3年以内に全ての科目に合格すればOK!
試験日程は、令和7年度は8月3日(日)に実施されました。
例年この頃に実施されています。
受験地は北海道、宮城県、東京都、愛知県、富山県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県です。
また、受験料は17,000円(非課税)です。
さて、「熱分野」と「電気分野」を選択するということは、免状の効果は違うの?という疑問が湧くと思います。
これは、どちらを選択しても効果は一緒!同じ資格となります。
「熱分野」「電気分野」共に科目は4科目で、そのうち、共通科目が1科目あります。
4科目全てを合格すれば晴れて試験突破!
残すは実務経験を1年積むのみです!
ちなみに、合格基準は各科目60%以上です!
エネルギー管理士試験には科目合格制度があり、3年で全科目を合格すればOKです!
『4科目も勉強する時間取れないよ』という方にとっては、1年で2科目合格できれば残りは1年間少しづつ勉強ができるため、3年計画での受験が可能です。
注意事項として、共通科目である「エネルギー総合管理及び法規」に科目合格した場合、共通科目であるものの途中で「電気↔︎熱」の分野を変更して受験したいと思った際に、受け直す必要があります。
また、受験料が高いことや受験地が限られるため、なるべく少ない回数で合格を目指す方が堅実です。
最短で合格したいという方は、通信講座も視野に入れるといいかと思います。
おすすめは「アガルートアカデミー」です。
電験三種でも1位としていますが、講師が教員免許を持っているなど、指導のプロであることや、現場資格に特化したSATが提供していることが特徴です。
電験三種の通信講座比較を参考にしてみて下さい。↓
「忙しい社会人向け!」電験三種の通信講座を比べてみたら一択だった件
エネルギー管理士の場合電験三種の半額程度です。電験三種の受験も考えている方はエネルギー管理士で通信講座を受講し、電験三種は独学でという選択も良いでしょう。
- 「熱分野」の科目
- 科目Ⅰ:エネルギー総合管理及び法規(電気共通)
- 科目Ⅱ:熱と流体の流れの基礎
- 科目Ⅲ:燃料と燃焼
- 科目Ⅳ:熱利用設備及びその管理
- 「電気分野」の科目
- 科目Ⅰ:エネルギー総合管理及び法規(熱共通)
- 科目Ⅱ:電気の基礎
- 科目Ⅲ:電気設備及び機器
- 科目Ⅳ:電力応用
「熱分野」と「電気分野」合格率はどっちが高いの?
①残念ながら近年分野別合格率は発表されていない・・・
②でも平成24年度までのデータによれば「熱分野」が高い傾向にあった!
③全体では30%越え!!
以下に合格率を整理してみました。
近年、全体での合格率は30%越えと高くなってきており、比較的合格しやすくなっている可能性があります。
分野別で見ると、平成24年度までしか公表していないため近年は分かりませんが、「熱分野」の合格率が高い傾向にありました!
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 平成27年度 | 10,537 | 2,454 | 23.3% |
| 平成28年度 | 10,468 | 2,108 | 20.1% |
| 平成29年度 | 10,558 | 3,002 | 28.4% |
| 平成30年度 | 9,912 | 2,770 | 27.9% |
| 令和元年度 | 9,830 | 3,207 | 32.6% |
| 令和2年度 | 7,707 | 2,828 | 36.7% |
| 令和3年度 | 7,684 | 2,454 | 31.9% |
| 令和4年度 | 7,766 | 2,636 | 33.9% |
| 令和5年度 | 8,137 | 3,074 | 37.8% |
| 令和6年度 | 8,558 | 3,150 | 36.8% |
| 令和7年度 | 8,300 | 2,783 | 33.5% |
- 分野別合格率(平成24年度まで)
| 実施年度 | 全体 | 熱分野 | 電気分野 |
|---|---|---|---|
| 平成20年度 | 20.6% | 25.6% | 15.0% |
| 平成21年度 | 29.6% | 29.4% | 29.7% |
| 平成22年度 | 35.1% | 43.1% | 25.4% |
| 平成23年度 | 19.8% | 18.2% | 21.8% |
| 平成24年度 | 23.3% | 28.0% | 16.7% |
まとめ
「電気分野」は電験3種合格直後、もしくは今後受験予定の方にオススメ
ここまで取得メリットや試験概要、合格率を見ていきましたが、「熱分野」と「電気分野」どちらを選択するか。
皆さんはいかがでしょうか。
これから取得に向け私も勉強をしていくため、勉強法は都度発信していければと考えていますが、「電気分野」は特に電験をベースとしているため、電験3種合格直後の私は「電気分野」を選択します。
「熱分野」は危険物取扱者やボイラー技師取得直後の方に良いと聞きます。
とはいえ、私も取得していますが、難易度が全然違うことから応用がどれほど可能かは分かりません。
「電気分野」は、電気工学科卒業者や電験取得者はより取っ付きやすく、勉強時間を短縮できます。
また、エネルギー管理士取得後に電験三種を受験しようと考えている方も、電気分野がおすすめとなります。
しかし、合格率を見ると、それ以外の方は「熱分野」での受験が最適解では無いかと考えます。
どちらを選択するにせよ、合格を目指して一緒に頑張りましょう!


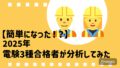

コメント